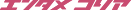記事入力 : 2023/11/26 10:46
「軍需品としての同志」…私は日本の責任を明瞭に問いただした【朴裕河教授寄稿】
朴裕河教授の反論-金潤徳記者の批判に答える
11月7日付の朝鮮日報で、金潤徳(キム・ユンドク)記者が「大法院(最高裁に相当)判決は無罪だが、朴裕河(パク・ユハ)の主張が正しいわけではない」として、私の著書『帝国の慰安婦』を批判した。その骨子は、同志愛・売春的強姦(ごうかん)を主張し、被害者に対する嫌悪を呼んでいるというものだ。だが大法院の判決は、まさしく訴訟の主張でもあったそうした認識が、事実ではないというものだ。金記者は判決文を読まずに、判決について書いたように思える。
何より私は、「同志愛」という言葉を使わなかった。「同志的関係」「同志的側面」「同志性」などの単語を用いただけだ。そうした単語を通して喚起しようしたものは、当時の朝鮮は日本との関係において中国やオランダのように「敵」ではなく、植民地であったという事実だった。既存の運動が、朝鮮を日本の植民地ではなく戦争相手とフレーム化し、そのせいで慰安婦問題の解決が遅れているという事実を理解するに至ったからだ。
『帝国の慰安婦』は、朝鮮人慰安婦問題を1990年代に東欧やアフリカで起きていた部族間強姦のケースと同様の「拉致/強姦=戦争犯罪」と規定し、法的責任を問いただしてきた既存の学問および運動の問題を指摘し、対立中だった両極端を批判しつつ第3の道を模索しようと提案した書籍だ。サブタイトルを「植民地支配と記憶の闘争」と付けた理由でもある。
従って、私の著書における「同志的関係」とはひとえに、朝鮮人女性は敵ではなく被植民地人として「(帝国)国家に動員」されたという意味だ。同時に、帝国の一員として動員されたので表面的には「同志的関係」であったが、堅固な「差別感情」もまた存在していたという事実も指摘した。小見出しの一つが「軍需品としての同志」である理由だ。「同志的関係」の適示は、帝国の責任をより明瞭に示してくれる。
軍需品として動員され、あすになれば死ぬかもしれない異国の地の厳酷な状況の中でも、日本軍との心理的連帯は存在した。私はその事実を、ほかならぬ支援団体(挺身〈ていしん〉隊問題対策協議会)が作った証言集を通して知った。行間に息づいている当事者らの人生と記憶を、単に「被犯罪人の心理」と見なし、「過度の愛着」という冷たい診断を下すように仕向けたのは、歴史に理想を投影しようとする欲望かつエリート女性の傲慢(ごうまん)だ。「慰安婦は日本軍を世話する存在」(日本軍慰安婦、また一つの声)と語っていたペ・チュンヒさんの言葉を、金記者は、おそらく単に洗脳された者のたわごとだと考えたいのだろう。だが、暴力の複雑さについての無知が生んだ、そうした「人間に対する無理解」(同コラムより引用)の方が、当事者らにとってはより残忍だろう。
売春婦だと主張する人々と、強制連行だとひたすら主張する双方から、私は同種の売春嫌悪を読み取った。従って『帝国の慰安婦』では、いわゆる売春かどうかは全く重要ではなかった。非難対象となった「自発的売春」は引用であって、「売春的強姦」も私は慰安婦を否定する人々を批判する脈絡の中で用いた。故に「売春を目的とした朝鮮人女性も少なくなかったと(朴裕河が)強調」したという金記者の主張は、単純誤読を超えて歪曲(わいきょく)であり、陰害(ひそかに他人を害すること)だ。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 朴裕河教授に「親日」の烙印を押した人々、韓国大法院判決に立場を表明せず 2023/10/27 15:08
- 韓国左派も右派も『帝国の慰安婦』を誤読した【朴裕河教授寄稿】 2023/11/05 11:10
- 朴裕河を打ちのめしたこん棒【朝鮮日報コラム】 2023/10/28 11:36
- 朴裕河教授「私が告発された『帝国の慰安婦』訴訟、ハルモニではなく周りの人たちが起こした」 2022/09/02 19:04
- 『帝国の慰安婦』朴裕河名誉教授、民事控訴審で勝訴 2025/01/23 11:05
- 韓国最高裁は共に民主・李在明代表の逆転無罪判決を破棄して自ら判断を【3月29日付社説】 公選法違反事件裁判 2025/3/29 11:25
- 憲法裁で9戦全敗中なのに…謝罪代わりに弾劾棄却された韓悳洙首相を再び弾劾で脅す共に民主党【3月26日付社説】 2025/3/26 14:25
- 法律上は「270日以内」のはずが909日…共に民主・李在明代表の公選法違反事件裁判、きょう控訴審判決【3月26日付社説】 2025/3/26 13:45
- 「代行」韓悳洙首相の弾劾棄却で9戦全敗の共に民主党は「代行の代行」崔相穆・副首相の弾劾訴追を撤回せよ【3月25日付社説】 2025/3/25 14:05