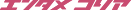記事入力 : 2021/06/20 17:00
【コラム】AI技術で私教育に立ち向かう韓国の公教育
まだ高校生だった2005年、「水準別教室」という制度が学校に初めて登場した。数学・英語の科目で、1年の内申の成績上位50%を「実力クラス」、下位50%を「努力クラス」と名付けて別々に集め、授業を行った。「オーダーメード型の教育」を試みたわけだが、数百人の生徒のうち半数は劣等生のレッテルを貼られてしまい、私教育への依存度は全く解消しなかった。
当時、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権は公教育の強化策として「修能等級制」を打ち出した。大学修学能力試験(修能。大学入学共通テストに相当)の成績が標準点数なしに等級のみで出てきて、相対的に内申が重要になった。1989年生まれの生徒の間で「内申を一度でも駄目にしたら名門大学への進学は永遠にお流れ」という恐怖感が醸成され、内申専門塾が生まれた。かといって大学入試に修能や論述が全く反映されないわけでもなく、総合塾も論述塾もよい商売だった。「死のトライアングル」という単語が流行したのもこのころだ。
公教育を生かすと称して入試制度にメスを入れる旧態は、政権が変わるたびに繰り返されてきた。しかし公教育が主導権を取り戻したことはない。入試制度を複雑にするだけだった。勉強がよくできる生徒も、そうでない生徒も、答えは私教育で探した。私教育が入試政策にふさわしい人材像を商品のようにつくり出している間に、2019年基準で韓国の私教育費の規模は21兆ウォン(現在のレートで約2兆700億円。以下同じ)にまで膨れ上がった。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連ニュース
- 4歳・7歳児も入試塾通い…激化する韓国の私教育に海外メディア「出産忌避の原因」 2025/03/22 11:15
- 韓国の成人の8人に1人「食事代わりにスナック菓子を食べている」 2025/03/07 17:25
- 韓国小学生のなりたい職業、2位に「医師」が浮上…1位は 2023/11/27 11:32
- 「韓国人の人種差別と外見至上主義は本当にひどい」 韓国で2年暮らしたベトナム系女性の主張 2023/07/20 11:34
- 韓国最高裁は共に民主・李在明代表の逆転無罪判決を破棄して自ら判断を【3月29日付社説】 公選法違反事件裁判 2025/3/29 11:25
- 憲法裁で9戦全敗中なのに…謝罪代わりに弾劾棄却された韓悳洙首相を再び弾劾で脅す共に民主党【3月26日付社説】 2025/3/26 14:25
- 法律上は「270日以内」のはずが909日…共に民主・李在明代表の公選法違反事件裁判、きょう控訴審判決【3月26日付社説】 2025/3/26 13:45
- 「代行」韓悳洙首相の弾劾棄却で9戦全敗の共に民主党は「代行の代行」崔相穆・副首相の弾劾訴追を撤回せよ【3月25日付社説】 2025/3/25 14:05