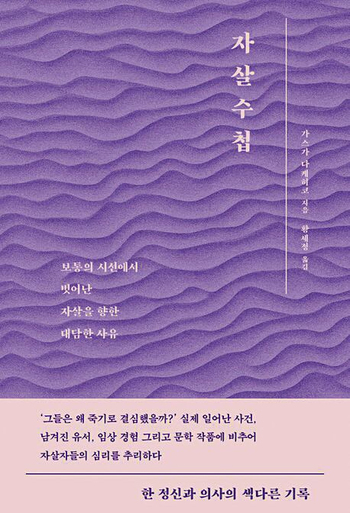記事入力 : 2025/04/13 09:05
「財布をなくした」という理由でなぜ命まで絶ったのか…日本の精神科医が自死事例を分析
【新刊】春日武彦著、ファン・セジョン訳『自殺手帳』(クレタ刊)
1918年、大阪の17歳の女工は、化粧品の使い方を間違えて顔が黄色くなってしまい、同僚にからかわれ、線路に身を投げた。同年、高松のある主婦は、財布を無くしてしまったと思い、夫に申し訳ないという理由でホルマリンを飲んだ。ささいに見えることが、どうして取り返しのつかない選択につながったのだろうか。
精神科医の著者が臨床経験、実際の事件、残された遺書など数十の自死事例を分析した一冊。上の事例は、著者が分類した自死の7類型のうち「懊悩(おうのう)の究極としての自死」に該当する。ひとたび「精神的視野狭窄(きょうさく)」に陥ってしまったら、一つの悩みにとらわれて、最終的には自死以外の他の選択肢が考えられなくなるほど柔軟性が失われるのだという。
自死というテーマを深刻かつ悲痛に取り上げるよりも、むしろ自死の「不謹慎」な側面に集中した。「憂鬱(ゆううつ)なら精神科を訪れてください」といった無難な文章よりも、正面勝負が一つの作戦になり得る、というわけだ。むしろ、自死の累計を冷静かつ客観的に認識すれば、死と距離を置きたくなるのかもしれない。原題は『自殺帳』。344ページ、1万8000ウォン(約1840円)。
ペク・スジン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連ニュース
- 「日本にいつまで『謝罪しろ、カネを出せ』と言うのか」…在日韓国人・張本勲氏の苦言【5月13日付社説】 2023/05/13 18:13
- 警察官を殴って韓国警察大退学、15年後に警部特別採用に合格して被害者に接近試みる【独自】 2025/08/06 11:45
- 日本の目で見た日本は…加害者であり被害者であり敗者 2023/12/03 08:05
- 「いじめ加害者よ、お前も同じようにやられてみてどんな気持ち?」 2021/02/28 05:26
- 「被害者」ポジション争いを眺める九つの基準とは 【新刊】リリ・チュリアラキ著『加害者は皆、被害者だと言う』 2025/08/17 11:45