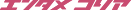記事入力 : 2024/06/17 17:35
中国の「風向計」・天安門広場【朝鮮日報コラム】
「内城」と「外城」に分かれた北京で天安門は内城の中心である皇城の正門だった。中国のインサイダーとアウトサイダーを区別する門でもあった。門前の広場は皇族と貴族のもので、外城の民は足を踏み入れることさえできなかった。
1911年に清朝が崩壊し、天安門広場に民衆が立ち入れるようになった。その時から天安門広場は中国が何を包容しているのかを見る目安となる「風向計」となった。中国初の反封建反帝国主義運動である「五四運動」が天安門広場で始まった。北京の大学13校の学生3000人が集まった。1949年10月1日には毛沢東がここで中華人民共和国の成立を宣言した。1970年代の文化大革命では紅衛兵数十万人が広場に集まり、1976年には文革を批判する第1次天安門事件(四五運動)がここで起きた。1989年4月に胡耀邦総書記が死去すると、全国で追悼ムードが高まり、同年6月4日の第2次天安門事件を招いた。
曲折の時代を経て、2000年代から天安門広場は皆に開放されたように見えた。改革開放政策が軌道に乗り、政治より経済が強調された大国に世界各地から外国人が集まり、天安門広場は過去の歴史には触れないまま、記念撮影ポイントとして位置づけられた。名実共に「新しい中国」を象徴する顔だった。
しかし、天安門広場は6月4日には、再び禁域に逆戻りした。天安門事件35周年となるその日、天安門城楼は「終日入場不可」という告知文を掲げ、市民の広場への立ち入りも制限した。
先月天安門広場の団体ツアーに参加した際には、外信記者という理由で現場から追い出される経験も味わった。ややこしい予約手続きを経て、旅行会社のガイドが同行したのに入場を拒否され、過去には可能だった「警察同行監視」の要求も拒否された。持ち物検査を2回も受け、旅券は帰宅を約束した後にようやく返してもらった。命令服従に慣れた警官は「上部の指針」という言葉だけを繰り返した。もどかしい気持ちで親交のある中国の記者にメッセンジャーアプリのウィーチャットで訴えたところ「会話はこれでやめよう」という反応が返ってきた。
巨大な経済を構築し、発展途上国を中心に国際的な影響力を確保した中国が「広場の閉鎖」を始めたことが実感できた。中国の政治体制、「戦狼外交」、「中国の経済モデル」などを露骨に同意し支持する人々だけが広場に入ることができる「選別作業」が進んでいる。
天安門広場ツアーに参加していた韓国人観光客の密かに話していた内容が記憶に残っている。一部の観光客は「記者1人のせいでツアーが遅れた。知っているべき人が中国の雰囲気も知らない」と言って、露骨にあざ笑った。ところが、いざ彼らが紫禁城に入ろうとすると、1メートルを超える自撮り棒を所持していたたという理由で見学を制限されたという。中国の内部に進入したとしても、いつでも追い出されかねないという事実を象徴的に示すエピソードではないか。
北京=李伐飡(イ・ボルチャン)特派員
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 「旧李王家東京邸」で思い浮かんだゼレンスキー大統領【コラム】 2025/4/6 11:45
- ダム建設反対論者たちの「選択的正義」【朝鮮日報コラム】 2025/4/6 11:35
- 「科学技術の天才」を次々と輩出する中国【萬物相】 2025/4/6 11:25
- 米国の「センシティブ国指定」巡り韓国の情報機関を調査するという共に民主党【コラム】 2025/4/6 11:05
- 落ち着いていた韓国国民、今後は国の正常化と危機克服を【4月5日付社説】 尹大統領罷免 2025/4/5 14:45