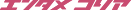記事入力 : 2024/01/09 11:35
日本の地震被災者の辛抱強さ【コラム】
年明け初日にマグニチュード(M)7.6の大地震に襲われた石川県の能登半島。避難所となっている輪島市の西小学校で今月3日、カワカミ・タダシさん(74)に会った。カワカミさんは「地震が起きてすぐに家の外に出たら、自宅はつぶれ、隣家は崩壊していた」と話した。カワカミさんは他の2人と共に崩壊した木造家屋に入り、80代の女性を救出した。「素晴らしいことをしましたね」と声を掛けると「皆そうしていますよ」と答えが返ってきた。
同じ避難所で、大阪から来たナカグチ・ヨシヒトさん(29)にも会った。地震で陥没・崩壊した道路を何とか抜けて車でやって来たのだ。ナカグチさんは「故郷であるこの地には父が住んでいて、大地震のニュースを聞いてすぐに休暇を取って駆け付けた」と話した。自衛隊員であるナカグチさんは「上司に尋ねたら、自分たちの部隊は災害支援に派遣されないということなので、幸い休みを取らせてもらえた」と説明した。避難所ではボランティアとして活動しており「あそこの前が自宅だが、まだ行けていない」「16年前にも大きな地震を経験したが、もう2回目なので慣れた」と話した。
輪島市の5階建てビルの崩壊現場で出会った70代の日本人男性は、地団駄を踏んだ。ビルの残骸の山にドリルで穴を開けている消防隊員を見ながら「町の焼き肉店の奥さんがビルの下敷きになって生き埋めになっている」と話した。男性自身も毛布1枚を持って避難所を転々とし、一日一食のおにぎりで命をつないでいる状態だが「昨日、娘さんは崩壊した現場から生きて救出されたが、奥さんが心配」と話した。
能登半島の地震では6日夜現在、日本人126人が死亡し、210人が安否不明になっている。家を失った被災者は3万人を超える。
今月2日から四日間、輪島市の災害現場の取材中に出会った日本人たちは、悲しみや怒りをあらわにするのではなく、まるで災害現場が日常であるかのように行動していた。一日の間に何度も襲ってくる余震の恐怖に、一日一食のおにぎりしか配られないという状況の中でも、停電・断水が続いてインターネットや携帯電話などがつながらない状況でもそうだった。災害の現場を取材するのは容易ではない。もしインタビューをお願いしたら、耐え難い苦しみの中にいる被災者に罵倒されることも一度くらいあるのではないか、と覚悟もしていたが、そのようなことは起きなかった。最悪の地震に何度襲われても、暴動や略奪といった混乱もなく再び立ち上がる日本人の原動力はこういうところにあるのだろう。
地震は単なる他人事だろうか。2016年の慶州地震(M5.8)、17年の浦項地震(M5.4)など、韓国でも最近、地震が頻発している。東海の海底には我々が知らない断層があるかもしれないとも言われている。韓国政府にはM7の大地震を前提にした対応マニュアルはあるだろうか。準備のない災害はもはや大惨事だ。今日も災害現場で黙々と耐えている日本人の被災者の方々に敬意を表する。
東京=成好哲(ソン・ホチョル)東京支局長
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 韓国最高裁は共に民主・李在明代表の逆転無罪判決を破棄して自ら判断を【3月29日付社説】 公選法違反事件裁判 2025/3/29 11:25
- 憲法裁で9戦全敗中なのに…謝罪代わりに弾劾棄却された韓悳洙首相を再び弾劾で脅す共に民主党【3月26日付社説】 2025/3/26 14:25
- 法律上は「270日以内」のはずが909日…共に民主・李在明代表の公選法違反事件裁判、きょう控訴審判決【3月26日付社説】 2025/3/26 13:45
- 「代行」韓悳洙首相の弾劾棄却で9戦全敗の共に民主党は「代行の代行」崔相穆・副首相の弾劾訴追を撤回せよ【3月25日付社説】 2025/3/25 14:05