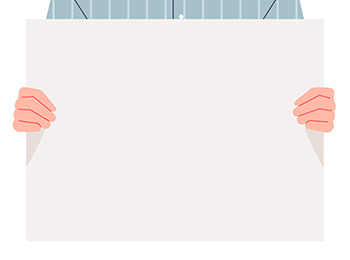記事入力 : 2023/12/11 17:05
中国「白紙デモ」から1年、何が変わったのか【朝鮮日報コラム】
「白紙で出したんだから、成績はいいはずがない」
中国で起きた「白紙デモ」から1年、北京で会ったある知識人は当時の運動をこう評価した。「白紙デモ」とは、昨年11月26日に上海で始まり、首都・北京など中国全土に拡大したゼロコロナ政策への抗議デモだ。参加者たちは当時、公安(警察)の制裁を避けるために、反政府スローガンなどが書かれたプラカードの代わりに真っ白な紙を掲げて街に繰り出した。中国ではめったに見られない大規模デモが発生したため、外信は「中国人たちが政府に立ち向かい始めた」と評価した。
しかし、1年が過ぎた現在、中国人たちはデモ以前よりもおとなしくなった。大衆メディアや芸術作品についても、反体制メッセージに対する自己検閲は強化され、私的な場でも国家指導者に対する批判は自制するような雰囲気だ。「習近平のライバル」と言われた李克強前首相が死去したときも、SNS(交流サイト)上では李前首相に対する再評価は匿名で書き込まれた。白紙デモが中国人にとって、「抵抗の経験」ではなく「国による厳しい統制に遭った」という記憶として残り、「傷弓の鳥(一度弓矢で傷つけられた鳥は、弓の弦音を聞くだけで恐れおののく意から、前の事に懲りて後の事を極端に警戒する人の例え)」が増えてしまったようだ。
白紙デモをけなすつもりはないが、「三日天下」「竜頭蛇尾」だったということは否定できない。実名を出して戦うデモ隊の主役もいなければ、中心的な役割を果たす組織もなかったせいだ。デモの目標が「ゼロコロナ政策の即時解除」なのか「政府の謝罪」あるいは「体制変化」なのかが明確ではなかった。デモの過程で北京大や清華大など名門大学の学生たちは、大学当局の目を気にして立場表明の文書すら出さなかった。対照的に、中国政府はデモ発生翌日から参加者らを探し出して警告・処罰するというやり方で一気に事態を鎮静化させた。
白紙デモ以降、中国で発生した大小のデモや公の場での抗議は「上訴」に近い動きだった。ガラスの天井でも生まれたかのように、中国人たちが非難を浴びせる対象は地方政府や下級官僚にとどまった。今年8月に中国が豪雨に見舞われた際、北京と雄安新区を洪水から守るために河北省保定市が「濠(ほり)」の役割を果たし、その結果同市の被害が大きくなったが、住民らの批判は中央政府ではなく地方の役人に向けられた。中国人にとってもはや政府は打倒・批判の対象ではなく、すがるべき「兄貴」なのだ。
今後、中国人が国家に対抗して戦う可能性はほとんどないとの分析も聞かれる。新疆ウイグル自治区と香港に対する中国政府の統制を目の当たりにし、白紙デモを通じて自分たちの限界を知った中国人の間に、「抵抗しても無駄だ」という認識が根付いてしまったのだ。
中国人は抵抗しないだろうという予想は、中国は変わらないだろうという結論へとつながる。米中の競争の中で、かたくなに計画経済・一人体制をつくり上げてきた中国は、もはや内部的に変化する可能性までも遮断しているからだ。韓国は、このような中国の姿が今後も続くと想定して戦略を練るべきだと考える。
北京=イ・ボルチャン特派員