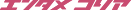記事入力 : 2022/09/04 07:00
韓中日、最強の防衛力・攻撃力を持つイージス艦確保競争
韓国は今年7月に4隻目のイージス艦「正祖大王」を進水した。これまでの世宗大王級(7600トン)よりも大きくなったのはもちろん、対空ミサイルSM6など弾道ミサイルによる迎撃能力も持つ。レーダー探知距離は1800キロに達し、最大で1800以上の目標を探知・追跡できる。韓国は今後、正祖大王級のイージス艦2隻をさらに確保する計画だ。これにより2028年には合計6隻のイージス艦を保有することになる。
韓国、中国、日本の3カ国が先を争ってイージス艦の導入を進める理由は、イージス艦が持つ戦力の比重が徐々に高まっているからだ。南シナ海はもちろん、台湾海峡や東海・西海を巡る3カ国の対立が激しくなり、イージス級駆逐艦が持つ戦闘能力がさらに必要になっているからだ。とりわけ韓国と日本の場合、北朝鮮の核と弾道ミサイルの脅威に備えるためイージス艦の役割がさらに高まっている。つまり北朝鮮の弾道ミサイルを探知・追跡し迎撃する「ミサイル防衛(MD)体制」の核心の一つがすなわちイージス艦だ。
最新のイージス駆逐艦は陸地に対する長距離からの攻撃力も大きく強化されている。日本の新型イージス艦の場合、特に射程距離が1000キロに達する艦体地ミサイルも搭載する計画だという。遠い海の向こうから地上の目標を正確に攻撃する武器を持つということだ。そのため日本はこれまで100キロだったミサイルの最大射程距離を延長する作業を進めている。
これに対して中国は新型駆逐艦の確保と同時に現在3隻の空母を2035年までに6隻に増やす計画だという。中国の海軍力はすでに量的には米軍の極東地域の海軍を上回っているとの見方もある。日本の防衛白書によると、中国海軍艦艇の総重量は224万トンで、韓国(28万トン)、日本(51万トン)、米第7艦隊(50万トン)、台湾(20万トン)を全て合計したものよりも多い。
東京=成好哲(ソン・ホチョル)特派員
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 不正選挙疑惑払拭に向け模擬投開票実施した韓国選管をパク・チュヒョン弁護士が質問責め 6月3日次期大統領選 2025/4/11 20:15
- 韓国・忠清南道知事 日本大使と会談=自治体交流など議論 2025/4/11 20:08
- 尹氏が大統領公邸から退去 支持者と抱擁も=韓国 2025/4/11 18:20
- 尹氏が大統領公邸から退去 「国のため新しい道探す」=韓国 2025/4/11 17:40
- 韓日中情報通信相会合 7年ぶり開催=デジタル分野の協力策議論 2025/4/11 16:10