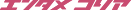記事入力 : 2013/07/28 06:45
「儒教打倒を叫んだ文化大革命で儒教復活」
尹輝鐸・韓京大教授が論文
儒教の伝統を破壊したとされる中国の文化大革命(1966-76)がむしろ儒教的な伝統を復活させ、それが現在の「新中華主義」につながったとの研究結果が示された。
韓京大の尹輝鐸(ユン・フィテク)教授(中国現代史)はこのほど「中国文化大革命期の反伝統と伝統」と題する論文をまとめた。
文革期に儒教は「身分秩序を維持しようとする反動的思想」と見なされ、毛沢東は林彪と孔子を批判する「批林批孔運動」で儒教を否定し、中国史を儒家と法家の闘争として捉える「儒法闘争」を掲げて、法家や秦の始皇帝を擁護した。
これについて、尹教授は毛沢東が秦の始皇帝のイメージをうまく仕立て上げたと指摘する。尹教授は「プロレタリア独裁という建前の下で、個人的な専横をためらわなかった毛沢東の専制主義的政治を法家的な進歩活動として合理化し、称賛した」と分析した。
文革期の毛沢東の専横は、秦の始皇帝に似た「伝統的専制主義」の様相を帯びており、中国史の中で脈々と受け継がれた儒教的専制主義が法家という美名の下で「復活」していたとの見方だ。さらに、毛沢東個人に対する崇拝で、毛沢東と人民の関係が「父子」「皇帝と臣下」に似た関係に変質したというのが尹教授の見方だ。
尹教授の指摘によれば、儒教文化に端を発する祖先崇拝儀礼が、結局は文革時期の個人崇拝として復活しており、それは北朝鮮の故・金日成(キム・イルソン)主席が主体(チュチェ)思想を掲げ、結果的に朝鮮の伝統的イデオロギーである儒教に依存したのと同じ幻想だった。さらに、中国の専制主義的伝統を支える「忠孝」「礼」「先公後私(私事より公を優先する)」の要素は、改革開放とともに「中華民族」「中華の伝統」が強調される中で再評価され、「新中華主義」の中心的要素になった。
兪碩在(ユ・ソクチェ)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
<記事、写真、画像の無断転載を禁じます。 Copyright (c) Chosunonline.com>
関連ニュース
あわせて読みたい
- 21世紀の文化大革命? 中国で「情報員」の大学生が教授を監視 2022/10/29 10:13
- 習近平主席の「文化大革命」…K-POPにとっては好材料 2021/09/20 05:05
- 【コラム】頭が割れても文在寅…「テッケムン」式の文化大革命 2020/11/08 10:01
- 【コラム】文在寅大統領の「積弊清算」はまるで文化大革命 2017/11/25 05:03
- 英国記者が暴いた「文化大革命のトラウマ」 2024/08/11 11:05
- 1950年6月に北朝鮮軍がソウル大病院で1000人銃殺…真実和解委がようやく「虐殺」認定【独自】 2025/4/3 09:05
- 「一度ももらったことない」「収入ゼロ」 デビュー6年目EVERGLOWの中国人メンバーが告白 2025/3/20 11:15
- 歌手キム・ジャンフン「大韓民国のほとんどすべての文化が死んだ」 チケット販売不振で順天公演中止 2025/3/19 11:35
- 盗品と判明した古書「大明律」、韓国当局が宝物指定取り消し 2025/3/12 11:25
- 日本の韓半島通が見た北朝鮮外交…「数少ないカードを使い回す」 2025/2/9 11:15