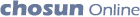コラム
韓国合計特殊出生率0.78人・日本1.26人…格差はどこに起因するのか【コラム】

昨年の日本の合計出生率は1.26人だが、韓国は0.78人だ。韓日はもちろん、東アジア諸国も深刻な低出生率に頭を抱えている。お隣日本もいまだに低い出生率を見せてはいるが、韓国の立場からすると日本との格差は広がる一方だ。韓国は2001年に出生率が1.30人となったことで、日本(1.33人)に逆転されて以降、約20年間一度も追い付いていない。韓国の出生率が1.0人を上回っていた時期など本当にあったのかと疑いたくなるほどだ。
こうした韓国と日本の出生率格差は一体どこから来るのだろうか。韓国に住む日本人専門家に会って、普段気になっていたこの問題について聞いてみた。同専門家は、意外にも日本は地方大学が持ちこたえているからだと答えた。日本には地方ごとに名門大学があり、あえて東京に集まらなければならない理由はそれほど多くないが、それが韓国よりも子どもを多く産む重要な要因の一つとなっているというのだ。
もちろん、日本の場合、伝貰(チョンセ、毎月の家賃の代わりに保証金としてまとまったお金を預ける賃貸制度)制度が存在しないため韓国のように結婚費用として1億ウォン(約1100万円)を超える資金が必要ない上、大学入試の準備も韓国に比べて厳しくないため、学校外教育に関する問題も韓国ほど深刻ではないという。韓国で結婚のための最も高いハードルとして挙げられる、そして低出生率の最も大きな要因として挙げられる住居と教育に関する問題が、韓国に比べてそれほどひどくないと言える。さらに、地方の名門大学が持ちこたえていることも無視できない要因の一つだ、というのが彼の見解だった。
彼の話を聞いて今年のQS(Quacquarelli Symonds)大学評価を見てみたところ、日本の名門私立である慶応、早稲田の前に京都大、大阪大、東北大、名古屋大、九州大、北海道大と地方大学が6校もあった。そのすぐ後ろには筑波大、広島大、神戸大などが並んでいた。こうした大学が存在するため、地方で勉強のできる学生があえて無理して東京に出てくる必要もなく、日本企業も新入社員を採用する際に地方大学出身者を適切に配慮することが、出生率の最悪になるのをある程度防いでいるというのだ。
それでは韓国はどうだろうか。2023学年度の全国188大学のうち、定時募集(修学能力試験〈修能=日本の大学入学共通テストに当たる〉を通じた入学者募集)の競争率が3対1を下回る大学が計68校(35.2%)に上った。定時は群別に3回志願できるため、競争率が3対1を下回ると定員割れと見なされる。このうち86%(59校)が地方大学だった。最後のとりでとされる地方を拠点とする国立大学も揺れている。釜山大、慶北大、忠南大、全南大、全北大なども毎年2月になると新入生を追加募集するのに忙しい。地方を拠点とする国立大学の2021年度の自主退学生は全体で6366人と、5年前の16年(3930人)に比べて1.6倍となった。
人口学専門家であるソウル大学保健大学院のチョ・ヨンテ教授は「韓国が超低出生率国家となった根本的な原因はソウルと首都圏への途方もない集中」とし「途方もない集中が物理的な密度だけでなく、若年層の競争心理、不安感をも高めたことで出生率を低下させている」と説明する。チョ教授は、首都圏集中を解決しなければ、住居、教育、保育問題などの個別案件にどんなに集中してみたところで、低出生問題を解決するのは至難の業と力説する。
政府がグローカル(Global+Local)大学30事業を始めたばかりだ。30の非首都圏大学を選び出し、5年間にわたって1000億ウォン(約110億円)ずつ延べ3兆ウォン(約3300億円)を支給する大型事業だ。今年10大学を選定する予定だが、先日15大学を1次として予備指定した。考えてみると、この事業に大学構造調整、地方大学の再生だけが懸かっているわけではない。この事業が成功してこそ、首都圏集中を緩和する方向に進むことができるだろう。地方にしっかりとした大学が30校あれば、首都圏に集まる心理をある程度緩和できるのではないか。グローカル大学30事業の成否が低出生率の克服にも重要な変数として作用しそうだ。
キム・ミンチョル論説委員