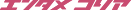記事入力 : 2015/01/02 11:34
「すしの始まりは街のファストフード」 日本の職人が語る
少しばかり誇張を加えれば、そのすしのサイズは握りこぶしほどの大きさだった。今の一口サイズのすしの3倍はあるように感じた。このすしを握ってくれたのは、ソウル・汝矣島の63ビル58階にある日本料理店「SHUCHIKU」のすし職人、高島康則さん(47)。20年にわたり韓国ですしを握ってきた高島さんは「150年前に生まれた当時の江戸前ずしはこれくらいのサイズがあった」と記者に説明してくれた。江戸とは東京の昔の名前だ。高島さんは「江戸前ずしは今のすしの原型だ」と語った。
日本で魚を使ったすしを食べ始めたのは7世紀とされる。フナなど淡水魚の内臓を取り除き、塩漬けして中にご飯を詰め込んだ。これは韓国の「シッケ(食醢)」とよく似ている。16世紀からは木枠に飯と魚を詰め込み、短くて数日、長い場合は数カ月にわたり熟成させて食べるすしも登場した。ところが短期な江戸の人たちは、このように長い間熟成するのを待つことができなかった。
高島さんは「18世紀中ごろ、江戸城前の屋台で商売をしていた人たちが、酢飯に魚の身をのせて売り始めた。これは完成まで1日もかからないため、当時としては文字通り『ファストフード』だった。人気が出てくると、同じものを作る店が次々と出てきた。屋台の客たちは立ち食いして腹を満たしたり、あるいは家に持ち帰って食べたりしていた」と説明した。
当時のすしは貧しい庶民が食事代わりによく食べていたので、サイズはかなり大きめで量も多かった。高島さんは「最近のすしはシャリ30グラムにネタ15グラムが標準だが、18世紀にはその2倍から2.5倍はあり、2回か3回に分けて食べなければならなかった」と語る。冷蔵庫がない時代だったため、しょうゆに漬けたマグロや塩漬けしたコハダ、ゆでたエビやイカなどが使われたという。高島さんは「今食べている生の魚をのせたすしは、まだ50年ほどの歴史しかない。シャリも戦後になって少しずつ小さくなった」と説明した。
1995年から韓国で働いてきた高島さんは「今は日本と韓国のすし文化に大きな違いはなくなったが、1990年代半ばごろ、韓国に初めて来たときは『オタマジャクシずし』という少量のシャリに長く大きな魚がのったすしがはやっていた。赤身の魚を好む日本人とは違い、白身の魚を好むお客さんが多かった」と話した。高島さんはさらに「韓国のお客さんは鮮魚よりも活魚を好むが、この点は以前から日本とは違う」と当時を振り返る。おいしいすしを見分ける方法を高島さんに尋ねると「表面はしっかり握ってあり、中は柔らかくなければならない。串を刺して持ち上げることができるくらいしっかり握られ、それでも口に入れると飯粒がすっと広がり、ネタと調和するように感じるようなすしがおいしいすしだ」と答えた。
金成潤(キム・ソンユン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 1950年6月に北朝鮮軍がソウル大病院で1000人銃殺…真実和解委がようやく「虐殺」認定【独自】 2025/4/3 09:05
- 「一度ももらったことない」「収入ゼロ」 デビュー6年目EVERGLOWの中国人メンバーが告白 2025/3/20 11:15
- 歌手キム・ジャンフン「大韓民国のほとんどすべての文化が死んだ」 チケット販売不振で順天公演中止 2025/3/19 11:35
- 盗品と判明した古書「大明律」、韓国当局が宝物指定取り消し 2025/3/12 11:25
- 日本の韓半島通が見た北朝鮮外交…「数少ないカードを使い回す」 2025/2/9 11:15