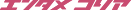記事入力 : 2014/06/22 09:11
キャンパスにあふれる漢字を読めない歴史学徒たち
漢字分かれば簡単な単語、学生ら意味も分からず丸暗記
ぽっかり「穴」開いた語彙力
漢字分かれば簡単な単語、音は知っていても意味知らず学習に支障
国語辞書引いてもさらに混乱
「先生、質問があります。『ホウキ』って何ですか?」
これは、ソウル市内の私立大学史学科で教えているA教授が数日前、新入生オリエンテーションで学生と話していたときに受けた質問だ。「蜂起(ほうき)」とは「虫のハチ(蜂)」に「起こる」と書いて、「ハチの群れのように大勢の人々が一斉に反乱などの行動を起こすこと」という意味だ。「歴史学科に志願しておきながらそんなことも知らないのか」と注意しようとしたが、周りの学生たちもみんな分かっていなさそうな顔をしていた。
■漢字知らず歴史学専攻する大学生
学生がよく分かっていない歴史用語はこれにとどまらない。朝鮮王朝時代、学識があり官僚を輩出するソンビという階層が受けた政治的迫害を意味する「士禍」、志を同じくする人々が集まった団体を意味する「朋党(ほうとう)」、西洋勢力が起こした事変を意味する「洋擾(ようじょう)」…。深刻な例では、戦争で大勝したことを意味する「大捷(たいしょう)」という言葉を、単に大きな戦争を意味する「大戦」と同じだと勘違いしている学生も多かった。
その単語を構成している漢字を知っていればすぐに意味が分かるはずなのに、教科書にはハングル文字だけが書かれているため、意味も分からないまま丸暗記に精を出していたというわけだ。A教授は「だからといって、戊午(ぼご)士禍を『戊午年(1494年)にソンビが迫害された事件」、丙寅(へいいん)洋擾を「丙寅年(1866年)にフランスが朝鮮に侵攻してきて起こった戦争」のようにいちいち解釈して話すわけにはいかない」と話した。
■意味の解釈できず英単語のように丸暗記
歴史科目だけではない。数学でも「等号」や「帯分数」という用語を初めて習うとき、漢字も一緒に習って「互いに等しいことを示す符号」「整数が分数を帯びているもの」という意味であることを知れば、はるかに理解しやすいはずだ、と学者たちは指摘する。
理科も漢字が分かれば、両生類は「陸地でも水の中でも生息できる生き物」、齧歯(げっし)類は「歯で物を齧(かじ)る生き物」、樹枝状細胞の「樹枝状」は「木の枝の形」の意味だとすぐに理解できる。だが、漢字を知らなければ単語を逐一丸暗記しなければならない。
兪碩在(ユ・ソクチェ)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
- 今日の歴史(3月30日) 2025/3/30 00:00
- 「尹大統領弾劾デモ」参加の若者らがチョークで大量の落書き、景福宮横の道路を終日占拠 2025/3/29 14:45
- 韓国検察、文在寅前大統領に出頭要請【独自】 元娘婿のタイ・イースター・ジェット特別採用疑惑 2025/3/29 11:55
- 3度目の不出廷「証人・李在明」に過料500万ウォン 大庄洞事件裁判 2025/3/29 11:15
- 「掃除の邪魔」 殺虫剤の付いたコメをまいてハト11羽殺害、50代女を逮捕 /仁川 2025/3/29 08:30